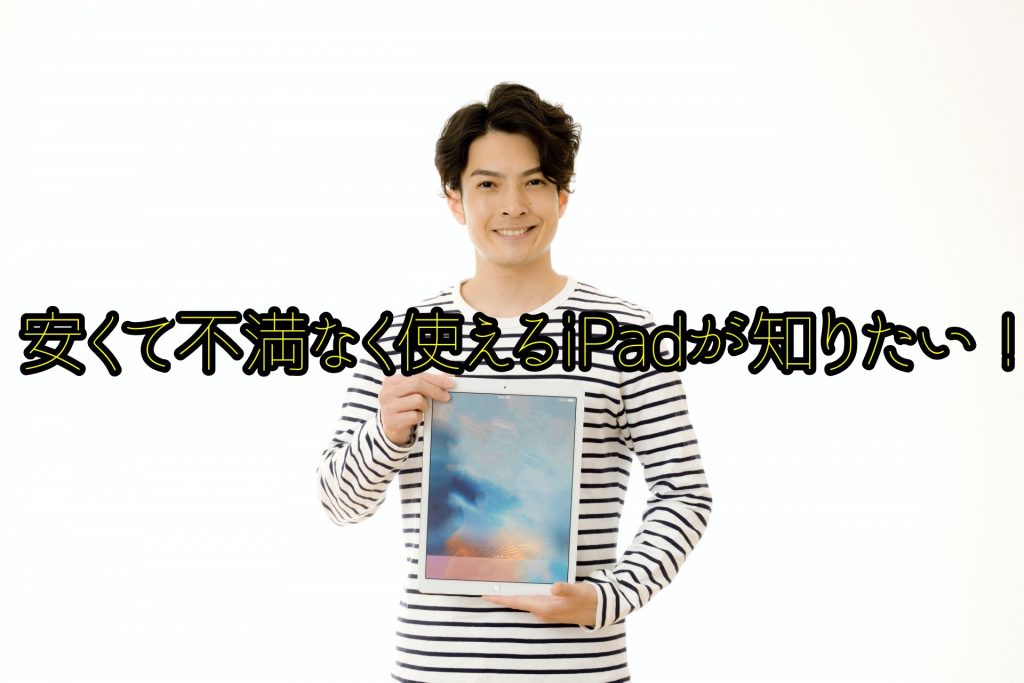「散らかった書類がたくさんあり、どこから手を付けたらいいのかさえわからない・・・」
「一度しっかりと書類を片付けたが、結局また散らかってしまう・・・」
「すぐに探している書類が見つけ出せる整理の仕方が知りたい!」
ズボラで書類整理に悩んでいるあなたはこんな悩みをお持ちのことでしょう。

今では整理整頓が人並みにできると思っている私ですが、
ひと昔前までは典型的なズボラだったため、
書類の整理整頓が全くできずよく整理整頓できる親に怒られてばかりでした。
しまいには親から「いったい誰に似たんだろうねえ」と言われる始末・・・

そのころは書類の片付けや整理整頓自体もすごく嫌いでしたので
片付けられないジレンマ
散らかるジレンマ
注意されるジレンマ・・・
私も昔は嫌というほど経験をしました・・・
しかし年令を重ねることで、
散らかったものを片付ける意識から散らかさない意識へと変化をしていきました。
そして今では数時間を欠けて片付けるという作業はほとんどしなくても片付いているクセが付き、
昔を知らない人からは昔から整理整頓ができたの!?と言われるくらいにまでなりました。

この記事では書類整理で悩んでいるあなたにデータで残すやり方と紙のまま残すやり方を組み合わせることで、
書類が散らかりにくくなり、
大片付けする必要がなくなり、
探している書類がすぐに見るかる
このようになるコツを解説していきます。
・ズボラでも簡単に ”職場” の書類を整理する5ステップ
・ズボラでも書類整理できる人に共通する3つの考え方
・まとめ
ズボラでも簡単に ”家” の書類を整理する5ステップ

家の書類を整理できる5ステップを紹介します。
②全ての書類をいるものといらないものに分ける
③いるものの書類の中から書類のままとして残すものと、データ化していいものとに分ける
④データ化してもいい書類をスキャンしてデータ化する
⑤新たな書類が発生した時、書類をどう処理するのか判別できるようにする
①データ化するのに必要なものを揃えておく

書類を分類してからでもいいですが、
最初にデータ化するのに必要なものを揃えておきます。
私が提唱する書類整理は、
書類をデータ化することですので、
データ化に必要なものをこれから紹介します。
スキャナー

書類を読み取るスキャナーです。
後から紹介しますがスマートフォンでのスキャナーアプリでも十分可能ですが、
よりキレイにデーター化するのであれば専用のスキャナーがオススメです。
スキャナーと一言で言っても用途によっていくつかの種類に分けられます。
書類をデータ化できるスキャナーは3種類に分類できます。
♢シートフィードタイプ
同じサイズで大量の書類を連続で一度で処理できる万能型なスキャナーです。
書類をロール型で巻き込んでスキャンしますので、写真をスキャンするのには向いていません。
♢ハンディタイプ
本体の持ち運びが簡単にできるので、どこの場所でもスキャンすることができます。
基本的には1枚ずつ読み取るタイプです。
♢フラッドヘッドスキャナー
コピー機のように書類をガラス台に固定して読み取るてタイプです。
一般家庭に普及している複合機のスキャナーと思ってもらえばいいです。
書類を保護できる利点はありますが、作業効率はよくないです。
スマートフォン(タブレット)用スキャナーアプリ

キレイに書類を保存するには専用のスキャナーが一番のオススメですが、
安いものではないだけに極力お金はかけたくない・・・
と思う方であれば、スマートフォン(タブレット)用スキャナーアプリでデータ化するのも一つの方法です。

カメラ性能やアプリ機能と日々向上していますので、
専用スキャナーと比較さえしなければ気にならない画像として保存できます。
スキャナーアプリは写真を撮ることで画像を取り込めるので、
どんな書類でもデータ化できるのが利点です。
逆に1枚ずつ写真を撮って画像を取り込んでいきますので、
数十枚の書類をデータ化するとなると、作業効率は悪くなってしまいます。
スマートフォンスキャンのオススメアプリを紹介します。
紹介するアプリは全てAppleのIOS、Android共に対応しています。
♢Microsoft Office Lens

マイクロソフト社で出している無料のスキャナーアプリです。
カメラを書類に向けるとデータ化したい書類の四隅を自分で指定して保存します。
もちろん、マイクロソフトのオフィス(Word、Excel、PowerPoint、Outlookなど)との相性は抜群です。
♢Adobe Scan
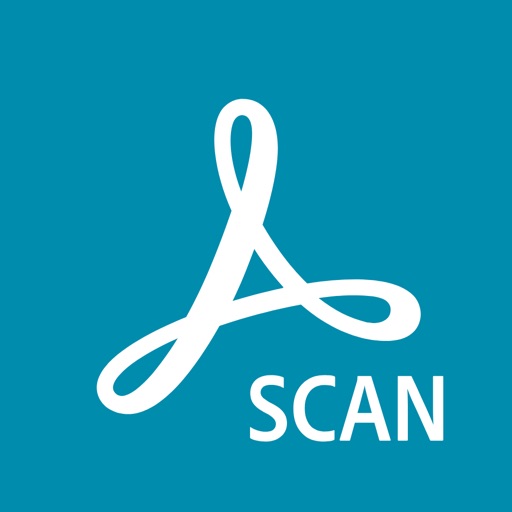
一部の人には有名ですが、アドビはプロフェッショナル向けの画像編集ソフトの最大手の会社です。
最大の特徴が、カメラを書類に向けると書類を自動で認識し、自動でシャッターを押してくれるのが、非常に便利です。
スキャンするだけで見るならば、他と比べて高性能なスキャンアプリと言えます。
裁断機

基本的に書類のみならば必要ありませんが、本やカタログをデータ化するには背表紙を裁断する必要があります。
カッターで切るとなると、キレイに切ることができませんし危険ですので、裁断機を使うことをオススメしたいです。
②全ての書類をいるものといらないものに分ける

最初の作業として、書類をいるもの、いらないものとに選別します。
いる・いらないの分別は意外と迷ってしまいますよね。
うまく選別できる方法として、
本当にいらないものだけをいらない方にすればいいのです。
選別に迷っている書類は、とりあえずいる方に残してください。
あくまでも目的は書類整理し、
書類自体を減らす事です。
書類を減らす方法は、
書類をデータ化することで減らすことになりますから。
ですので、少しでも迷ったら、いる方に選別してください。
③いるものの書類の中から書類のままとして残すものと、データ化していいものとに分ける

いちばん重要な分別が必要な書類から、書類のまま残しておくものと、データ化しても問題ない書類に分別する作業です。
この判断に関しては、書類の種類ごとに私の基準を説明します。
健康診断表

健康診断表の結果通知をそのまま残していませんか?
私は最新の結果以外はデータ化しています。
最新の結果だけ残すのは病院や医院へ受診した時に必要な時があるからです。
使用済み通帳

使用済み通帳も私は処分をしています。
ほとんどの銀行ではネットバンキングが使えるようになっています。
銀行にいかず家の中で振り込みや取引履歴を見ることができますので、
登録することをオススメします。
過去の取引履歴をネットバンキングで見れますので、
使用済みの通帳も保存する必要はありません。
破棄するか、
もしくはどうしてもデータをとっておきたければデータ化してから廃棄することをオススメします。
(専用スキャナーよりはスマートフォンスキャナーの方がやりやすい)
銀行や保険会社からの通知ハガキ

銀行や保険会社から来る通知のハガキはそのままとっておいてしまい、そのうち山となってしまいがちです。
証書や契約書以外はとっておいても必要ないものですので、データ化してから処分しています。
給与明細

会社の給与明細は確定申告の有無によって変わってきます。
確定申告をしない人は特に必要はないものですので破棄するなり、
データ化して破棄すれば問題ありません。
会社員でありながら確定申告が必要な方は、
給与明細や源泉徴収票は紙でもデータ化するなどして残しておく必要があります。
昔は源泉徴収票の紙自体が必要でしたが、
今は源泉徴収票に書かれていることを確定申告の書類に書かないといけませんので、
取り扱いには注意してください。
公共料金の領収書

家計簿をつけている方であればどのくらい使用したかの記載に必要ですので、データ化したほうがよろしいでしょう。
特に気にしていない方は破棄してしまいましょう。
カード・携帯電話明細書

カードや携帯電話の明細書はメールで送る形に各社移行しています。
明細書を紙にこだわる方もいらっしゃいますが、結局散らかる原因にもなりますので、
メールで送られてくる形式に変更するのをオススメします。
手紙・ハガキ

手紙や年賀状などはほとんどの方はそのまま保管しています。
しかし、本当にそのままとっておく意味があるのか、
を考えてみると、無いんです。
でしたら、ためらわずデータ化しましょう。
④データ化してもいい書類をスキャンしてデータ化する

書類をそのまま残すものと、データ化するものと選別しましたら、
データ化できる書類をスキャンします。
スキャナーでアプリでデータ化するやり方はそれぞれですが、
スキャンしたデータをどこに保存するかについて説明します。
家庭用の書類に関してはインターネット経由で保存できるクラウドシステムで保存しています。
理由は、
データの安全性を考えてのことです。
一昔前はハードディスクやUSBメモリー、スマートフォンに掲載されているSSDなどの記憶媒体に保存していました。
しかしこれらは機械ですので使用していくうちに壊れてしまうものです。
壊れればデータは破損してしまいますので、
私はその危険性のないクラウドシステムで保存しています。
ではクラウドは100%安心なのか、
と言われると正直100%とは言えるものではありませんが、
少なくともハードディスクやSSDと比較すると危険度がかなり低いのは確かです。
もう一つの考え方としてクラウドシステムやハードディスク、SSD、USBメモリーと全てに共通して、
危険回避という意味で一箇所だけに保存しておかずに複数に保存しておくことで、
1つのデータ破損してももう一つが残っていればデータ消失を防げる、というやり方があります。
これは作業が確かに面倒にはなりますが、一番安価で安全なやり方です。
ちなみに私はクラウドシステムで同じデータを2箇所に管理しています。
どちらにしても、全てのものに完璧はありません。
各々(おのおの)でデータを危険回避することで大切なデータを守ることは必要となります。
⑤新たな書類が発生した時、書類をどう処理するのか判別できるようにする

④で大掛かりな書類整理が完了できましたが、この先は、2度と大掛かりな書類整理を行わないために日頃から気をつけることをお話します。
ちゃんとキレイにした後からでも、今までと同じように新たな書類は発生します。
新たに発生した書類を発生した時点でどのように処理するかを判断することがこれから先、求められます。
②③で説明したように
・いる書類なら書類として残さないといけないものか、データ化していいものかを選択する
書類が発生したらその都度、この選択を日頃から行なうことです。
これで、書類が再び増えてくる事はありません。
増やさないことで大掛かりな書類整理もやる必要がありません。
これは書類整理に限らず、普通の掃除でも同じことが言えます。
慣れるまで少し苦労するかもしれませんが、一度慣れてしまうと逆に書類を選択すること、そしてデータ化することが快感となってきます。
私が今、その状態です。
ズボラでも簡単に ”職場” の書類を整理する5ステップ

家庭での書類整理は家庭内の判断で自由にできるものですが、職場での書類整理はやることは変わりませんが、気をつける点が違ってきます。
会社という組織が絡みますので、個人の判断だけ書類を整理することは基本的にできません。
職場での書類整理の5ステップはこちらになります。
②個人文章のうち、データ化できるものとデータ化できないものに分別する
③データ化できるものはデータ化する
④データ化できないものはファイルなどで管理する
⑤新たに発生する書類、手元にある書類が個人文章なのか、共有文章なのか、を常に意識すること
では職場での書類整理を5ステップで見ていきます。
①自分の手元にある書類が個人文章か共有文章かを分別する

どの会社にも社内規則というものがあります。
その社内規則に書類の管理に関しても何かしら書かれているはずです。
まずは会社の社内規定を今一度読んでください。
書類(ここでは文章と書かせてもらいます)には
・共有文章
の2つに分けることができます。
個人文章とはどのようなものを指しているかと言いますと、
・個人の参考資料
のことです。
わかりにくいと思いますのでわかりやすく説明します。
文章を作成している途中の段階である
報告書を例にします。
紙で報告書を書いている途中の段階では個人文章です。
書き終わり提出された時点でこの報告書は共有文章となります。
個人の参考資料
同じく報告書を例にします。
報告書を書くのにある雑誌の記事が報告書の参考になると思い、雑誌からコピーをしました。
このコピーした資料は個人文章という扱いになります。
共有文章のコピー
再び報告書で説明します。
報告書を書きあげ後は提出するだけだが、今後のために報告書を自分の手元に置いておきたいと思い、コピーをしました。
このコピーは個人文章という扱いです。
この3つ以外の文章はすべて共有文章となるのです。
ではあなたの整理できない書類を見てください。
はたして個人文章に当てはまるのはどのくらいありますか?
思いの外、少ないのではないですか!?
実は書類整理ができなくて悩んでいた多くの書類が個人文章ではなく共有文章なのです。
ということは共有文章が社内でしっかり共有できれば、手元にある共有文章が手元から離れますので、自然と書類が減ることになります。
スタートとして自分の手元にある書類が果たして個人なのか、共有なのかを見定めて、分別することです。
しかしすぐに始めようと思っても会社全体がやらないと一人で進めようとして進めることができません。
まずは自分のできる範囲からスタートしていきましょう。
②個人文章のうち、データ化できるものとデータ化できないものに分別する
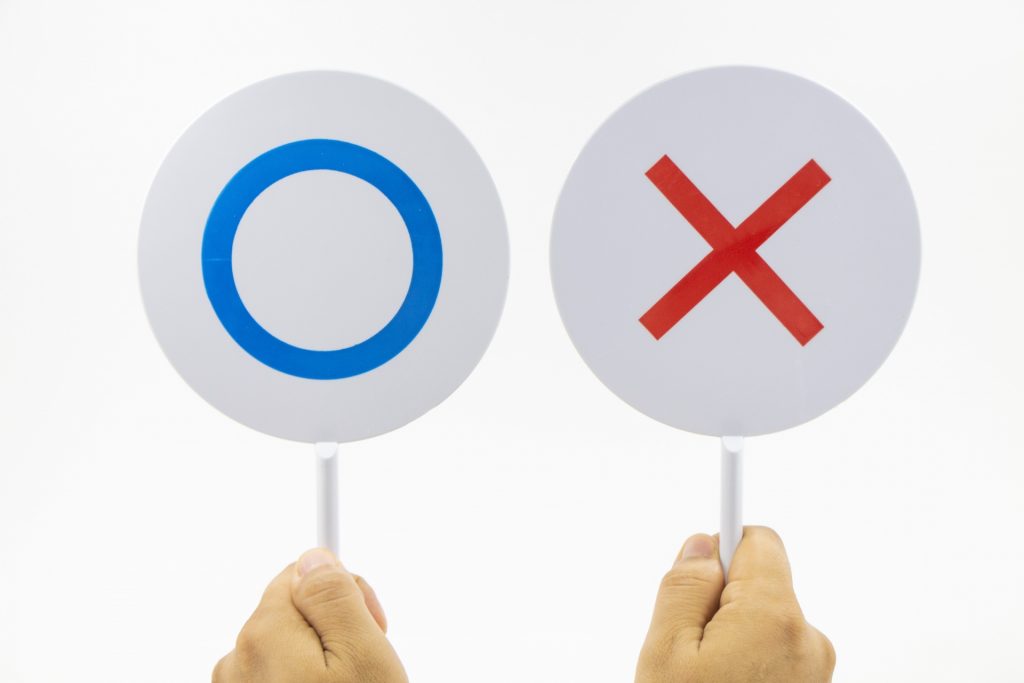
個人文章と共有文章の分別ができましたか?
分別して気付くこと、それは個人文章は意外と少なかったのではないでしょうか。
社内の書類が多い原因、片付かない原因として、社内で共有する書類が個人で管理していたために、書類の量が多くなってしまっていたのです。
共有文章の扱いに関しては、社内での話ですので、これ以上の話は進めません。
残った個人文章ですが、ここからデータ化できるものとデータ化できないものに分別してください。
ここでのデータ化できるか、できないかの基準ですが、私はこのように考えます。
・それ以外の書類は全てデータ化しない
家庭での書類整理では積極的にデータ化を進めていた私ですが、ここでは端切れが悪いですね・・・(笑)
他社からもらったパンフレットやカタログはデータ化した後、万が一情報流出しても被害がほとんどありません。
しかし個人文章をデータ化すると持ち運びしやすいことで情報流出の危険性が高くなってしまいます。
いっぽう書類のままですと持ち運びが情報ほど楽ではありませんので、その分情報流出の危険が低くなる、ということです。
③データ化できるものはデータ化する

データ化する上での注意点としては保存する場所です。
家庭の項でオススメしたクラウドシステムはIDとパスワードさえあればどのパソコンからも閲覧できますので、危険な面があります。
それ以外のパソコン内、外付けのハードディスク、SSD、USBメモリーで保存し、できればその記憶したものを就業時間外では会社で管理してもらうのが一番良いです。
データ化してもいいものは情報流出しても痛手にならないものをデータ化しているので、被害はほとんど無いでしょうが、それでも取り扱いは慎重にしたほうがいいです。
④データ化できないものはファイルなどで管理する

データ化できない個人文章はファイルなどで保存します。
ただ、個人文章はしっかり分別すればさほど多くはないはずです。
あくまでもしっかり分別すれば、の話ですが。
ポイントは自分が探しやすい管理法をしてください。
あくまでも”自分が”がポイントです。
書類自体の管理につきましてはまた別のところで紹介します。
⑤新たに発生する書類、手元にある書類が個人文章なのか、共有文章なのか、を常に意識すること

職場での書類整理について説明しましたが、個人さえ頑張ればいいという話でなく、どうしても会社などの組織が絡むことですので、そこでの難しさはあります。
しかし、一度しっかり書類を整理した後は、新たに発生する書類が個人文章なのか、共有文章なのか、個人ならデータ化できるか、できないかを常に考えることで、書類がたまることはありません。
家庭と同じことです。新たな書類ができきたらどのように分別するかを常に考えてください。
ズボラでも書類整理できる人に共通する3つの考え方

最後に散らかさない人の共通点を3つをピックアップしました。
②定期的に大掛かりな書類整理をせずに、一度整理ができたら二度と大掛かりな書類整理はしない意識
③新たな書類が発生したら判断を先送りせずに判断する
①書類を整理する意識ではなく書類を減らすことを意識する

整理整頓ができている人の中には物が沢山な人もけっこういます。
しかし、ズボラな人がたくさん物を持つと、散らかすだけです。
常に散らかさずにいるためには物を持たないこと、物がある人は片付ける意識以上に減らす意識を強く持ってください。
そのことで、つねにキレイな状態でいられるようになります。
②定期的に大掛かりな書類整理をせずに、一度整理ができたら二度と大掛かりな書類整理はしない意識

数時間を掛けて書類の大整理や大掃除をやり終えた時に、またやりたいなあーと思うでしょうか。
ほとんどの人はもうやりたくない・・・と思うでしょう。
しかし、残念ながらほとんどの人は、ある程度経過すると同じようにまた大整理や大掃除をするのです。
①で話をしたものを減らす意識を持つこと、または大整理や大掃除をしたくない意識を常に持つことでかわってくるはずです。
大整理や大掃除をしないためには、日頃の物を減らす行動が大切になってきます。
1日数分で済むことの積み重ねが◯時間もかけて行なう大掃除をやらずに済むことができるのです。
③新たな書類が発生したら判断を先送りせずに判断する

1日1日の積み重ねが散らかさずに済む一番の行動になります。
書類が発生した時点で分別を考えることで、新たな書類を適切に処理することができます。
分別の決断を先送りしたところで後にしても分別の決断は同じようにやらないといけません。
どうせ先でも後でも同じことをやらないといけないのなら先になってしまいましょう。
先にやることで課題が一つ消え、頭の中の悩みを一つ減らすことができますし。
まとめ

いかがだったでしょうか。
家庭でのケースと職場でのケースでは違うことが多々ありますが、根本的なことは変わりません。
書類を減らす、書類を増やさない
この2つを意識さえすれば、今までとは違った景色が見えてくるはずです。
それを続けていくことで、知らぬうちに今まで見るのも嫌だった書類が、そのうち新たな書類が出てきても苦に感じずに即決することが身についていることでしょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。